契約書や定款など、紙と印鑑での手続きに煩雑さを感じていませんか?
公証役場での手続きには時間や手間がかかり、「もっと効率的に進められたら」と感じる人も多いでしょう。
この記事では、2025年に向けて進む公正証書遺言のデジタル化について、その仕組みやメリット・注意点をわかりやすく解説します。
読めば、デジタル化された公正証書遺言の作成・保管方法が理解でき、スムーズな相続対策を進められます。
公正証書遺言デジタル化の背景と現状
高齢化社会における遺言ニーズの増加や、法務省・デジタル庁の政策を背景に、公正証書遺言のデジタル化が注目されています。
ここでは、なぜデジタル化が必要とされているのか、その理由と現状を解説します。
高齢化社会における遺言ニーズの増加
高齢化が進むなか、相続対策として遺言を作成する人が増えています。
終活への関心が高まり、自身の財産をどのように承継するかを明確にしておきたいと考える人が多いからです。
しかし、紙の遺言は手続きが煩雑で、作成や保管に手間がかかるのが現状です。
また、認知症など判断能力の低下により、遺言を作成できないケースも増えています。
遺言は意思能力があるうちに作成する必要があるため、早めの準備が重要です。
さらに、紙の遺言には紛失や改ざんのリスクもあります。
こうした問題を解消する手段として、デジタル化が注目されています。
デジタル化によって、高齢者だけでなく、多忙な現役世代もオンラインで遺言作成を進められるようになります。
これにより、誰もが手軽に安心して遺言を作成できる社会の実現が期待されています。
法務省・デジタル庁の取り組みと現状
法務省とデジタル庁は、国民の利便性向上と行政の効率化を目的に、電子公証制度の導入を進めています。
この制度が実現すれば、公正証書遺言もオンラインで申請や署名が可能になります。
ただし、2025年10月現在では、デジタル化が本格的に始まっている公証役場はまだ限られています。
公証役場にリモートでの証人立会いについて確認したところ、現時点では対応できないケースが多く、対面での手続きが基本です。
また、電子署名による完全オンライン化を試験的に導入しているのはごく一部の公証役場にとどまっています。
電子公証制度は、商業登記や不動産登記など他の行政手続きのデジタル化にも波及する見込みです。
政府は、安全性を確保しつつ、信頼性の高い電子署名・本人確認の仕組みを整備しています。
一方で、電子署名の偽造や個人情報の漏洩など、デジタル特有のリスクも懸念されています。
そのため、強固なセキュリティ対策と、利用者が安心して利用できる環境づくりが同時に進められています。
公正証書遺言のデジタル化で何が変わる?
デジタル化により、遺言の作成・保管・執行の各段階で大きな変化が起こります。
オンライン相談や電子署名、デジタルデータ保管など、主な変化を見ていきましょう。
オンラインでの事前相談・予約
従来は何度も公証役場へ行く必要がありましたが、デジタル化によりオンラインで相談・予約が可能になります。
自宅やオフィスからビデオ通話で公証人に相談できるため、移動時間や交通費を節約できます。
ただし、現時点ではオンライン相談が可能な公証役場は一部に限られています。
多くの公証役場では、本人確認や意思確認のために、引き続き対面でのやり取りを求めています。
また、リモートでの証人立会いは、制度面・運用面の課題が多く、今のところ実現していないのが実情です。
インターネット環境やデバイスの準備も必要で、オンライン手続きには一定のITリテラシーが求められます。
本人確認手続きがオンライン専用に追加される場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。
電子署名による遺言作成
最大の変化は、印鑑の代わりに電子署名を使用する点です。
電子署名は本人確認情報を含み、偽造や改ざんを防止できます。
利用には、信頼できる認証局が発行する電子証明書が必要です。
これはマイナンバーカードなどを通じて取得でき、有効期限や更新手続きにも注意が必要です。
ただし、現状では電子署名で遺言作成を完全に完結できる公証役場は限られています。
当面は、紙での署名や対面確認と併用する「ハイブリッド型」の運用が主流となりそうです。
電子署名を使う際は、対応ソフトや機器の準備が欠かせません。
事前に仕組みを理解しておくことで、スムーズな手続きが可能になります。
デジタルデータでの遺言保管
遺言をデジタルデータで保管することで、紙の紛失や毀損リスクを回避できます。
データは公証役場など信頼できる機関で保管され、必要に応じて迅速に閲覧・提出が可能です。
ただし、全国すべての公証役場がデジタル保管に対応しているわけではありません。
紙の原本を併用するケースが多く、完全電子化の実現には今後数年を要すると見込まれます。
不正アクセスやウイルス感染などのリスクに備え、セキュリティ対策を徹底することが欠かせません。
また、遺言者の死後に円滑に執行されるよう、相続人への共有方法など体制を整えておく必要があります。
公正証書遺言をデジタル化するメリット・デメリット
デジタル化には、手続きの効率化や安全性の向上といった利点がある一方、デジタル依存や操作の難しさといった課題もあります。
メリット:手続きの簡素化・効率化
オンライン相談や電子署名の導入で、公証役場への訪問回数を減らせます。
これまで数週間かかっていた遺言作成が、数日で完了するケースも想定されます。
さらに、紙の保管場所が不要になり、印紙代や交通費などのコストも削減できます。
メリット:安全性の向上
デジタル保管により、遺言の紛失や改ざんのリスクが大幅に減ります。
電子署名の活用で本人確認が厳格になり、偽造防止にもつながります。
また、公証役場がセキュリティ管理を担うため、安心して保管を任せられます。
ただし、電子証明書やデータのバックアップなど、利用者側の管理も重要です。
デメリット:デジタル環境への依存
パソコンやスマートフォンを使いこなせない人にとっては、操作が難しく感じられるかもしれません。
また、機器の故障や通信トラブル、電子証明書の期限切れなどによる不具合も起こり得ます。
これらのリスクを減らすには、定期的なメンテナンスとバックアップの実施が欠かせません。
不安がある場合は、紙の控えを併用するのも一つの方法です。
公正証書遺言のデジタル化に向けた今後のスケジュール
法務省・デジタル庁による法改正や実証実験が進められており、段階的な導入が予定されています。
法改正の動向
電子署名法や民法などの関連法令が改正され、電子署名の要件やオンライン手続きのルールが整備されます。
最新の情報は、法務省の公式サイトや専門家への相談で確認しておきましょう。
実証実験の実施状況
法務省とデジタル庁は、オンライン申請や本人確認手続きの実証実験を進めています。
これにより、高齢者にも利用しやすいシステム設計が検討されています。
現状では、都市部を中心とした限られた公証役場でテスト運用が行われていますが、今後の成果を踏まえて全国展開が検討されています。
段階的な導入計画
まずは一部地域で試験的に導入し、順次全国へ拡大する計画です。
利用者支援のための相談窓口やサポート体制も整備される予定です。
導入スケジュールを確認し、今のうちにデジタル環境に慣れておくと安心です。
公正証書遺言をデジタル化する際の注意点
デジタル化には利便性とともにリスクも伴います。
ここでは、安全に利用するための基本的な注意点をまとめます。
電子証明書の取得・管理
電子署名の正当性を証明する電子証明書は、マイナンバーカードなどで取得できます。
有効期限が切れると署名が無効になるため、定期的に更新しましょう。
証明書データを保存するUSBやICカードは、安全な場所で厳重に管理してください。
セキュリティ対策の徹底
強固なパスワード設定やウイルス対策ソフトの導入は必須です。
不審なメールやリンクを開かないなど、日常的な対策も重要です。
また、定期的なバックアップを取り、安全な場所に保管しておきましょう。
専門家への相談
弁護士や司法書士などの専門家に相談すれば、法改正や最新制度への対応も安心です。
費用はかかりますが、法的に有効な遺言を確実に作成でき、相続トラブルを防ぐ効果があります。
まとめ
公正証書遺言のデジタル化は、手続きを効率化し、安全性を高める大きな一歩です。
オンライン相談や電子署名を活用することで、時間と手間を大幅に削減できます。
しかし、2025年10月現在では、デジタル化に対応できる公証役場はまだ一部に限られ、リモート証人や完全オンラインでの作成は実現していないケースが多いのが現状です。
そのため、当面は対面手続きを基本にしつつ、一部デジタル化された仕組みを活用するハイブリッド型で進めるのが現実的です。
今後の法改正やシステム整備によって、誰もがオンラインで安心して遺言を作成できる時代が到来するでしょう。
制度の進展を注視しながら、専門家と相談して最適な方法で準備を進めてください。
都内の税理士・行政書士法人に勤務しています。
相続専門の行政書士として、コンサルティングや他士業との連携もしており、死後の手続きから生前相談(遺言や信託)にも精通。
年間面談件数は120件以上、豊富な知識と経験、話しやすさに定評をいただいております。
行政書士 登録番号:21082254 所属:東京会

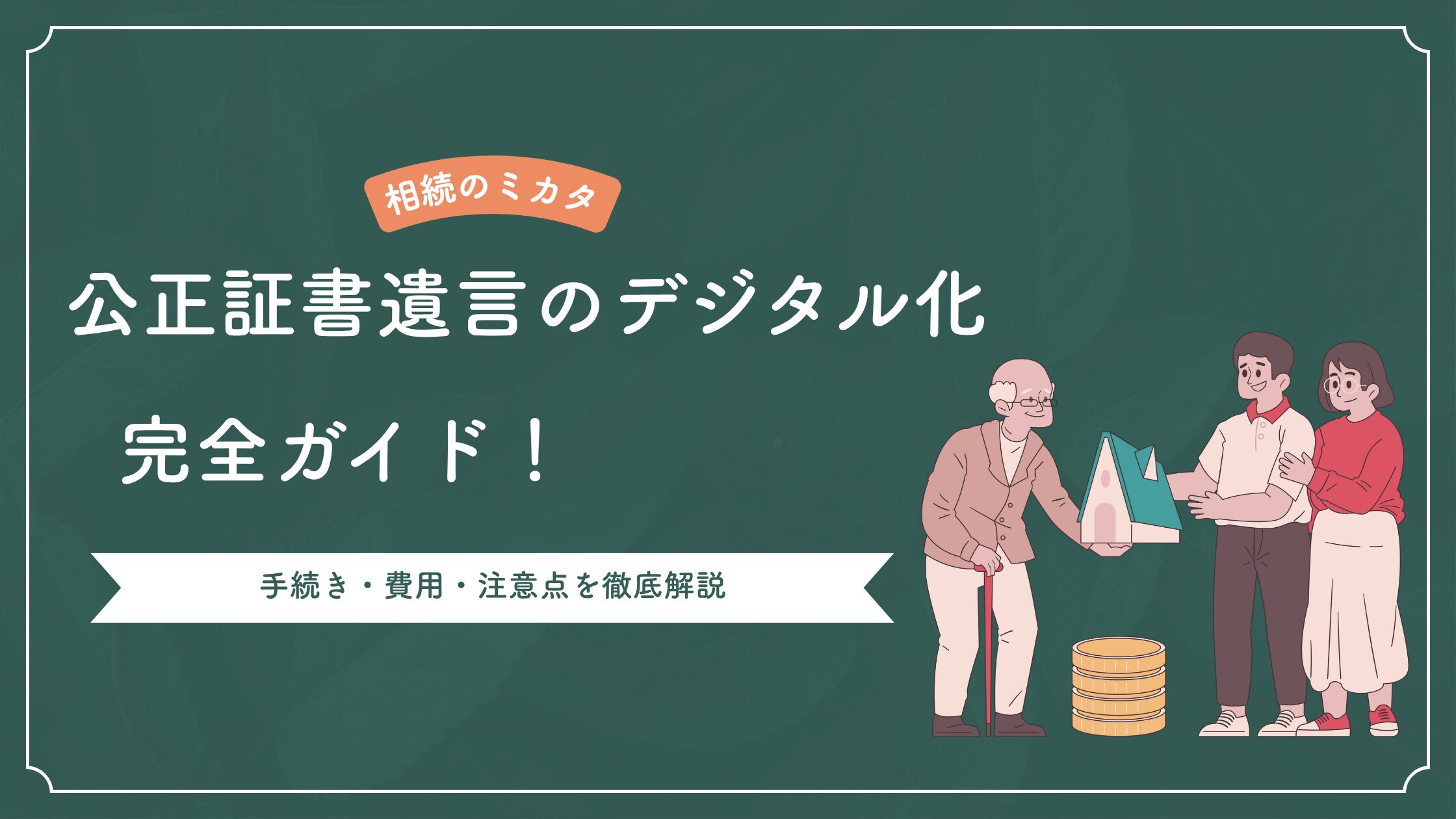

コメント