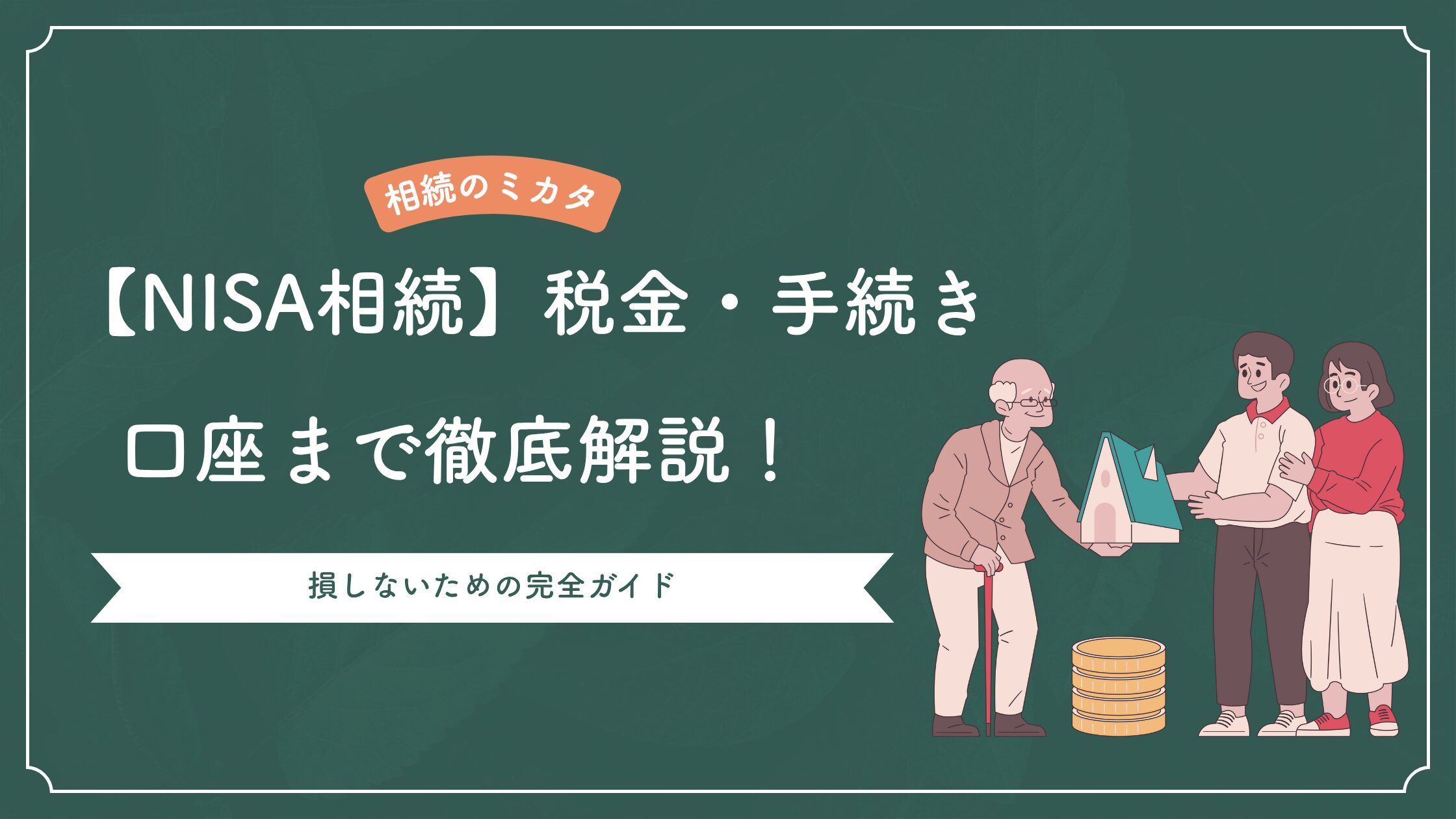NISA口座の相続で損をしないために知っておくべきこと
NISA口座の相続で、税金や煩雑な手続きに頭を悩ませていませんか?
NISA口座の相続は制度が複雑で、何から手を付けて良いのか分からない方も多いでしょう。この記事では、NISA口座の相続に関する税金の扱いや具体的な手続きの流れを、初心者にも分かりやすく解説します。
最後まで読むことで、NISA相続で損をせずスムーズに手続きを進めるための知識が身につきます。
NISA口座の相続とは?制度の基本を理解する
NISA口座の相続は、一般の預貯金や株式とは異なる扱いを受けます。
被相続人(亡くなった方)のNISA口座は、相続発生日で非課税の取り扱いが終了します。ただし、死亡時点までに得られた利益(含み益)は課税されません。
その後、相続人はNISA口座内の資産を一般口座または特定口座に移して引き継ぐことになります。
「相続人のNISA口座にそのまま引き継げる」と誤解されがちですが、実際には一度非課税枠が終了し、通常課税の口座へ移す仕組みです。まずはこのルールを理解しておきましょう。
一般NISAとつみたてNISA、相続時の違いを把握する
NISAには「一般NISA」と「つみたてNISA」がありますが、相続時の基本的な扱いはどちらも同じです。どちらのNISAでも、被相続人が亡くなった時点で非課税枠は終了します。
つまり、「つみたてNISAなら非課税のまま引き継げる」というのは誤りです。死亡時点での資産評価額は相続税の課税対象となり、相続人の課税口座に移した後の売却益や配当には所得税(約20%)がかかります。
相続手続きを進める前に、どちらのNISAを利用していたかを金融機関で確認しておきましょう。SBI証券や楽天証券などのネット証券では、ウェブサイトやアプリから簡単に確認できます。
相続におけるNISA口座の取り扱い:課税・非課税のルール
NISA口座の資産は、相続発生日の評価額で相続税の課税対象となります。ただし、死亡時点までの含み益には所得税がかからないという優遇措置があります。
また、次のようなケースでは相続税の負担を抑えられることもあります。
- 相続人が配偶者であり、配偶者控除の対象となる場合
- 相続財産の合計が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」(現行制度)以下の場合
ただし、NISAの非課税制度は被相続人の死亡とともに終了するため、相続後は通常の課税口座として管理する点に注意しましょう。
NISA口座相続の手続き:5つのステップで完全ガイド
NISA口座の相続手続きは複雑に感じますが、以下の5ステップで整理すると分かりやすくなります。
【ステップ1】金融機関への連絡:相続発生の報告
相続が発生したら、まず被相続人が取引していた金融機関に連絡します。
連絡が遅れると口座が凍結され、手続きが進まなくなるおそれがあるため注意しましょう。
SBI証券や楽天証券などの場合は、コールセンターや専用フォームで手続きを進めます。
【ステップ2】必要書類の準備:戸籍謄本、印鑑証明など
金融機関から案内された必要書類をそろえましょう。主な書類は以下の通りです。
- 被相続人と相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- NISA口座の残高証明書
印鑑証明書には有効期限(3〜6か月)があるため、提出直前に取得するのが安心です。
【ステップ3】相続人の確定:遺産分割協議を行う
相続人全員で話し合い、誰がNISA口座内の資産を引き継ぐかを決定します。
合意内容は「遺産分割協議書」にまとめて署名・捺印します。内容に不安がある場合は、弁護士や税理士など専門家に相談しましょう。
【ステップ4】資産移管手続き:NISA資産を課税口座に移す
相続人が確定したら、NISA口座内の資産を特定口座または一般口座へ移す手続きを行います。
NISA資産を相続人のNISA口座へそのまま移すことはできません。
相続人が新たにNISAで投資を始めたい場合は、自分名義で新規NISA口座を開設します。
【ステップ5】税務署への申告:相続税申告が必要な場合
相続財産の合計が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続税の申告が必要です。
NISA口座の評価額は被相続人の死亡日の時価で算出し、相続開始を知った日から10か月以内に申告書を提出します。
NISA相続で損をしないための注意点
非課税投資枠の理解と新規活用
被相続人のNISA枠は相続時に終了しますが、相続人自身が新たにNISA口座を開設すれば、自分の非課税枠を活用して運用を再スタートできます。
相続で受け取った資産をそのまま非課税枠に移すことはできませんが、得た資金を原資として新規投資を行うのは効果的です。
特定口座・一般口座との比較検討
NISA口座は非課税のメリットがありますが、年間投資上限が決まっています。
一方、特定口座や一般口座では利益に約20%の税金がかかるものの、損益通算が可能です。
投資額や目的に応じて、自分に合った口座を選びましょう。
専門家への相談:税理士、FPなど
相続税や手続きに不安がある場合は、税理士やファイナンシャルプランナー(FP)などの専門家に相談を。
費用はかかりますが、正確な手続きを行うことで結果的に節税につながるケースもあります。
まとめ
NISA口座の相続は一見複雑ですが、制度の基本と正しい手順を理解すればスムーズに進められます。
被相続人のNISA口座は非課税枠が終了する一方で、含み益には課税されないという優遇もあります。
相続税の基礎控除や金融機関への連絡期限を守り、損をしない手続きを進めましょう。
都内の税理士・行政書士法人に勤務しています。
相続専門の行政書士として、コンサルティングや他士業との連携もしており、死後の手続きから生前相談(遺言や信託)にも精通。
年間面談件数は120件以上、豊富な知識と経験、話しやすさに定評をいただいております。
行政書士 登録番号:21082254 所属:東京会