大切な人を亡くされた後、残された手続きは多く、精神的にも負担が大きいものです。特に、故人の確定申告は複雑で、何から始めたら良いのか途方に暮れてしまう方も少なくありません。しかし、ご安心ください。故人の確定申告をスムーズに進めるための「準確定申告」という制度があるのです。この記事では、故人の準確定申告に必要な手続きや書類、そして注意点などを分かりやすく解説します。これを読めば、相続手続きにおける負担を軽減し、気持ちに余裕を持って次のステップへ進むことができるでしょう。さっそく詳しく見ていきましょう。

準確定申告とは?故人の確定申告をスムーズに行うための制度
故人の確定申告は、相続手続きの中でも特に複雑で煩雑な手続きの一つです。しかし、税制上「準確定申告」という制度を利用することで、手続きを簡略化し、相続人の負担を軽減することができます。この章では、準確定申告の概要と、故人の確定申告におけるその役割について解説します。
準確定申告の対象者と申告期限
準確定申告は、亡くなった方が生前に確定申告が必要な所得(事業所得、不動産所得など)があった場合に相続人が行う手続きです。 具体的には、事業所得や不動産所得があった場合、2000万円以上の収入があった場合、複数の会社からの収入があった場合(ただし従たる給与が年20万円以下の場合は除く)、公的年金による収入が400万円以上あった場合、給与、退職金以外で20万円以上の収入があった場合、生前に株式や不動産などを売却し譲渡所得があった場合などが該当します。 ただし、会社員で2000万円以下の給与収入のみだった場合は、年末調整が済んでいるため不要です。 申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。期限を過ぎると加算税や延滞税が課される可能性があります。
準確定申告の申告先と納付義務者
申告先は、亡くなった方の住所を管轄する税務署です。通常の確定申告とは異なり、申告者の住所ではありません。納付義務は相続人に発生し、相続した割合に応じて負担します。相続人が複数いる場合は、相続人ごとに納付手続きが必要となる場合があります。
準確定申告に必要な書類を準備しよう
準確定申告には、いくつかの必要書類があります。この章では、必要な書類の種類と、それらを準備する際の注意点について解説します。
必要な書類リスト
準確定申告に必要な書類は、大きく分けて以下の通りです。
- 準確定申告書(国税庁ホームページからダウンロード可能)
- 準確定申告書の付表(国税庁ホームページからダウンロード可能)
- 亡くなった方の源泉徴収票
- 亡くなった方の給与所得・事業所得等の収入に関する書類(給与明細、収支内訳書など)
- 相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)
- 生命保険などの控除証明書(該当する場合)
- 医療費の領収書(医療費控除を適用する場合)
- 委任状(還付金の受取人を特定の人に指定する場合)
上記以外にも、事業所得や不動産所得があった場合は、収支内訳書(青色申告の場合は青色申告決算書)が必要となります。 書類の様式は、国税庁ホームページで最新版を確認することをお勧めします。 不明な点があれば、税務署に問い合わせましょう。
書類の収集と保管における注意点
書類の収集にあたっては、亡くなった方の書類の保管場所を確認し、重要な書類が紛失・破損しないよう注意深く保管することが重要です。 特に、源泉徴収票や給与明細などは、複数年にわたるものが必要となる可能性があります。 また、相続人が複数いる場合は、書類の共有方法を明確にして、スムーズな手続きを進められるようにしましょう。 不明な点や困難な点があれば、税務署や税理士に相談することをお勧めします。
準確定申告の手順をステップごとに解説
準確定申告の手続きは、いくつかのステップに分けられます。この章では、それらのステップを順を追って説明します。
相続人の代表者を決める
相続人が複数いる場合は、準確定申告の申告者を1名に絞る必要があります。 全員で連署して提出する方法と、相続人がそれぞれ申告する方法の2パターンがあります。 前者の場合、相続人の中から代表者を選び、代表者が税務署とのやり取りを行います。後者の場合は、相続人それぞれが申告を行い、申告内容に相違がないよう注意が必要です。どちらの方法をとるかは、相続人の状況に応じて判断しましょう。
必要事項を正確に入力しよう
準確定申告書には、亡くなった方の個人情報、所得情報、相続人の情報などを正確に入力する必要があります。 入力ミスや漏れがあると、処理に遅延が生じたり、修正が必要になったりする可能性があります。 特に、所得金額や控除額などは、正確な金額を記載するよう注意しましょう。 必要に応じて、税務署や税理士に相談しながら作成することをお勧めします。
申告書の提出方法
準確定申告書は、税務署への持参、郵送、または電子申告(e-Tax)のいずれかの方法で提出できます。e-Taxを利用する場合は、相続人の代表者がまとめて手続きを行う必要があります。 それぞれの方法にはメリット・デメリットがあるので、相続人の状況やITスキルなどを考慮して最適な方法を選択しましょう。 提出期限を守ることは非常に重要です。
準確定申告における注意点
準確定申告には、いくつかの注意点があります。この章では、それらの注意点について解説します。
申告期限を守ること
準確定申告の申告期限は、「相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内」です。 期限内に申告しないと、加算税や延滞税が課せられる可能性があります。 期限に間に合わない場合は、税務署に相談し、事情を説明することが重要です。 期限を意識し、余裕を持ったスケジュールで手続きを進めましょう。
必要書類を漏れなく提出すること
準確定申告では、必要な書類を漏れなく提出することが重要です。 書類が不足している場合、処理に遅延が生じたり、再提出を求められたりする可能性があります。 提出前に、必要な書類が全て揃っているか、もう一度確認しましょう。 不明な点があれば、税務署に問い合わせて確認することをお勧めします。
税務署への相談を積極的に利用すること
準確定申告の手続きに不安がある場合、または不明な点がある場合は、税務署に相談することをお勧めします。 税務署には、確定申告に関する相談窓口が設置されており、専門職員が丁寧に相談に乗ってくれます。 積極的に相談を利用して、スムーズに手続きを進めましょう。
よくある質問と回答
この章では、準確定申告に関するよくある質問をまとめました。
Q1:準確定申告の適用要件は?
A1:亡くなった方が生前に確定申告が必要な所得(事業所得、不動産所得など)を得ていた場合に適用されます。 具体的には、事業所得や不動産所得、2000万円以上の収入、複数の会社からの収入(ただし従たる給与が年20万円以下の場合は除く)、公的年金による収入が400万円以上、給与・退職金以外の20万円以上の収入、株式や不動産の譲渡所得などです。会社員で2000万円以下の給与収入のみの場合は、年末調整が済んでいるため不要です。
Q2:準確定申告の申告期限は?
A2:相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。期限厳守が重要です。
Q3:準確定申告で申告漏れがあった場合の対応は?
A3:申告漏れに気づいたら、速やかに税務署に申告し、修正申告を行う必要があります。 修正申告が遅れると、加算税などのペナルティが課される可能性があります。
Q4:相続放棄をしたら、準確定申告はしなくていいですか?
A4:相続放棄をした場合は、相続人ではないとみなされるため、準確定申告の義務はありません。
Q5:亡くなった人が年金受給者の場合、準確定申告は必要ですか?
A5:年金収入のみで、年間受給額が400万円以下の場合は、原則として不要です。
まとめ
故人の準確定申告は、相続人にとって複雑な手続きとなる可能性があります。この記事で解説した内容を参考に、手続きを進めてください。不明な点や不安な点があれば、税務署や税理士に相談することをお勧めします。期限を守り、正確な情報に基づいて手続きを進めることで、相続手続きを円滑に進めることができるでしょう。
なお、制度や必要書類は変更される可能性があるため、最新の情報は国税庁ホームページや税理士への確認をおすすめします。
準確定申告を滞りなく完了するには、相続に精通した税理士に依頼することがポイントです。
以下の記事で相続に強い税理士のポイントを解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
都内の税理士・行政書士法人に勤務しています。
相続専門の行政書士として、コンサルティングや他士業との連携もしており、死後の手続きから生前相談(遺言や信託)にも精通。
年間面談件数は120件以上、豊富な知識と経験、話しやすさに定評をいただいております。
行政書士 登録番号:21082254 所属:東京会

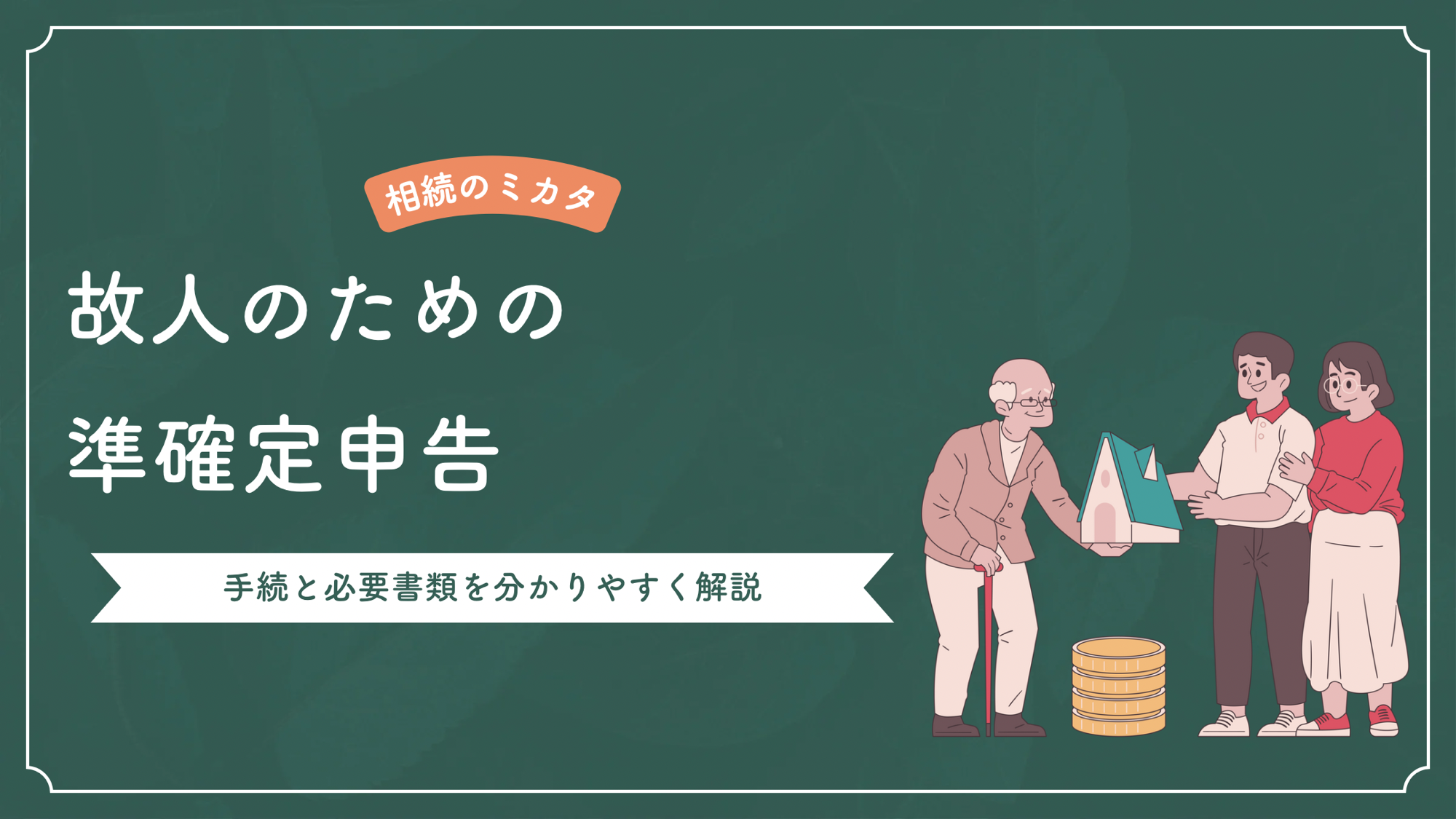
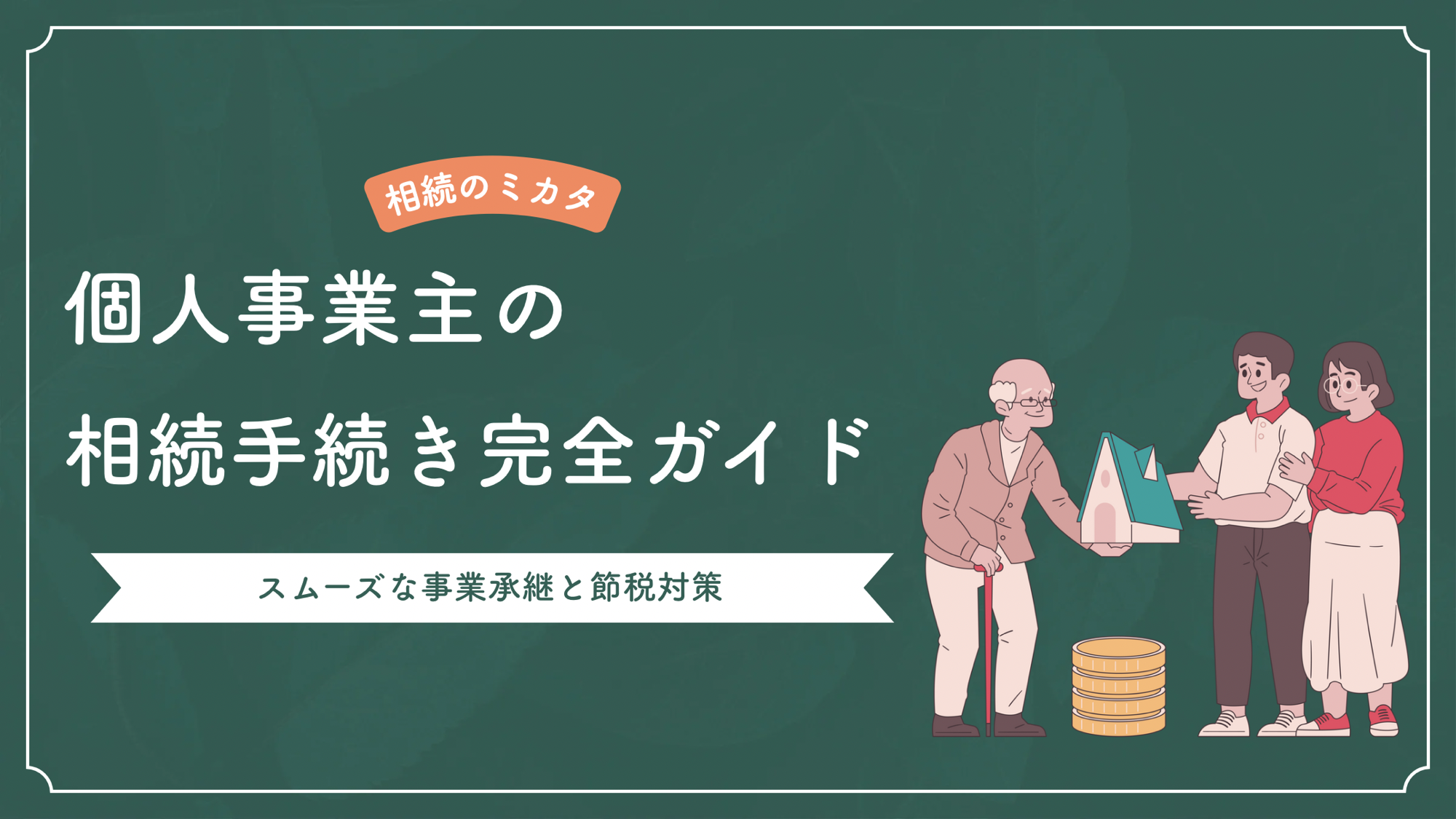
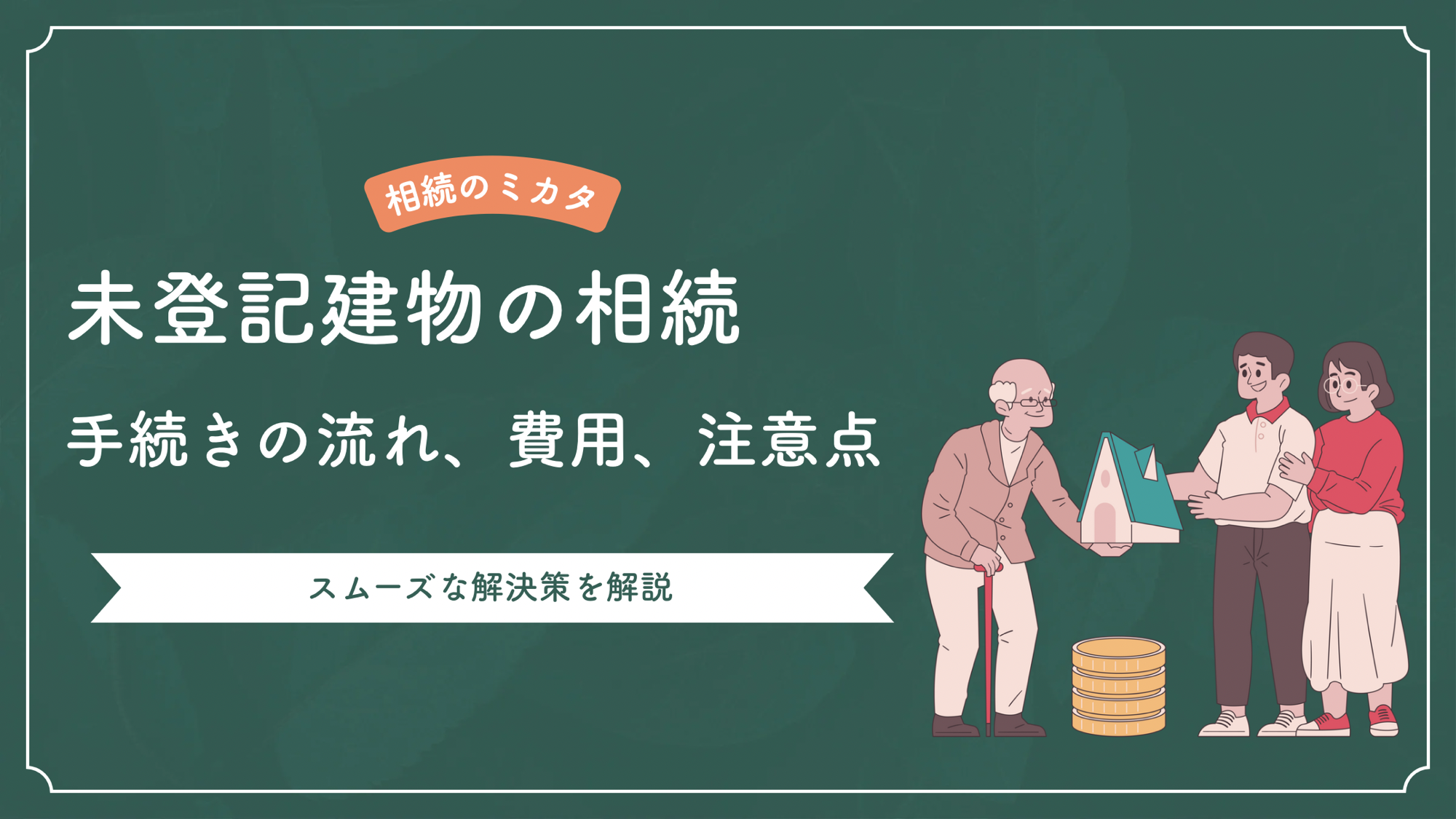
コメント